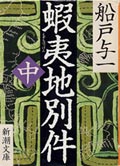2003年11月2日「学食だいすき」
学食はいいですよね。学食大好きです。あのスタンダードを地で行くメニューと味つけ。徹底したコストパフォーマンス。栄養のバランスも取れていて、量もきっちりあって食後の満足感を保障してくれます。
一昨日、トレーナーで行っている北大オーケストラの練習後にチェロセクションの皆と学食で昼ご飯食べました。最近トレーナーに呼ばれるのが日曜日の昼間か平日の夜ばかりでなかなか学食に行けませんでした。久しぶりに土曜の午前中に行ったので学食にいけました。ここ数年の大願成就です。学食は食後にまったりと過ごせる広いスペースもよいです。

上の写真は北大学食の”カレッジ盛り合わせ”(340円)。「そうそう、これなんだよ。これ!」と思わず言ってしまいたくなる学食然とした趣。この揚げ物中心のメニューは学食のメイン定食の王道です。わたしの出身校の獨協大学で言えば”獨協ランチ”に相当します。
(そういえば、4年ほど前に獨協オーケストラのOBオケのために10年振りに獨協に行ったら学食が変わっていて東武飯店からテナントも変わっていて”獨協ランチ”が別物になっていた・・。あれには愕然とした・・。)
北大は生協が入っているのでトレーに乗せて定食や惣菜を選んでいき、最後に清算する方式です。獨協大学は生協がなかったので食券方式でした。ちなみに70年代の大学紛争時代に大学側が学生自治会を押え込んだ大学には今だに生協と自治会が無いという話しを聞いたことがあります。獨協も自治会の代わりに「学友会」というのがあり、「学費の値上げに協力しましょう」なんてわざわざ貼らなくてもいいだろ、と思うようなポスターを学友会が貼ったりしてたので、紛争云々の話しには信憑性がありました。
第2の出身校の東京芸大は音校と美校にそれぞれ学食がありました。音校のはキャッスルという近代的な学食で、美校は大浦食堂という昭和初期に建てられたお寺を改造したようなレトロな建物の学食でした。この大浦食堂のメニューは建物同様、時代がかっていて楽しめました。焼き魚やおひたし、煮物などの惣菜が中心で、”バター丼”というバターしょうゆ味の丼が人気メニューでした。学食の王道メニューではありませんが下町の定食屋みたいでよかったです。値段的には一般の学食ほど安くはありませんでしたが・・。そういえば、芸大にも生協と多分自治会もなかったけど、そもそもこの大学に紛争があったのかが謎。
札響で働くようになってからは、練習場は芸術の森みたいな観光地だったり、キタラも観光地ではないけど洒落たレストランしかないので、どうしてもコンビニ弁当が中心になります。職員食堂のある職場が羨ましいです。
地方の演奏会の時はホールと役所が隣接していることが多いので、そういう時は役所の職員食堂に行きます。あと高速道路のサービスエリアの食堂も職員食堂チックな味と品揃えで好きです。北海道はラーメン屋は多いけど定食屋は少ないですよね。普通の味の定食屋となるともっと少ないです。普通がいいんですけどね。普通が・・。
2003年10月28日「『蝦夷地別件』の足跡を行く」
|
|
船戸与一の「蝦夷地別件」という小説を読みました。「国後・目梨の戦い」、「寛政アイヌの蜂起」として知られている1789年のアイヌと松前藩の戦いを描いた作品です。アイヌ関連の書籍は好きで昔から読んでいるのですが、実話に基づいたこの小説は「和人・悪v.s.アイヌ・善」という図式ではなく、想像力逞しく生々しい当時のアイヌ社会が描かれていてリアルで楽しかったです。 |
|
|
10月の道東演奏旅行を利用して「蝦夷地別件」の足跡を訊ねることにしました。当然こんな企画に乗る楽員はいなく一人旅でした(笑)。 左の地図が国後と目梨地方です。1は37人のアイヌが松前藩によって”処刑”されたノツカマップ岬。2は当時の目梨地方(現在の道東地方)の首都だった厚岸町。3は現在行くことが可能な日本の最東端、納沙布岬です。 |
|
|
左の写真は厚岸の遠景。分かりにくいですが、大きな厚岸湾(蠣の産地で有名)を横切る厚岸大橋があります。左手が陸側。右手が海側。まさに天然の良港。 |
|
|
北海道最古の寺の一つ国泰寺の山門。「第十一代将軍家斉公建立」とあり、葵の紋が扉に彫られています。幕府が東蝦夷地を松前藩より召し上げ直轄とした折、北方守備とアイヌ撫順の目的で設立した蝦夷三官寺の一つ。(有珠の善光寺、様似の等樹院) 小説の中では清澄が洗元に、自分たち僧が蝦夷に送り込まれた理由として、この寺の建立の名目を作るためと解いています。 |
|
|
国泰寺のとなりに厚岸郷土館があります。ちいさな資料館ですが、縄文期の土器から近代の農機具まで所狭しと並んでいます。左の写真はアッケシの惣長人イコトイが仙台藩より受けた陣羽織。実際イコトイが袖を通したと思うとワクワクする。 郷土館の隣にイナウ(儀式に使う御幣)があったので館の職員の女性に訊ねたところ、つい最近イチャルパ(先祖供養)があったとのこと。この女性はとっても熱心にいろいろ説明してくださった。国泰寺がなぜアッケシのこの場所に建立されたか、イコトイやオッケニ(イコトイの母、国後脇長人ツキノエの妹)が住むコタンはどこにあったのか?など長年疑問に思っていたことがいろいろと解明した。 4時から根室市民会館でリハーサルがあることも忘れ長居した。是非また訪れたい。 |
|
|
厚岸の地図。 1はイコトイやオッケニが住んでいた場所。当時のコタンの中心。2は国泰寺。この隣に運上屋跡がある。 3は小説の中で洗元と妻のハスマイラが養生所を開いていたと思われる場所。コタンに行くには山を降り、運上屋へは船で行く。となるとこの辺の場所と推定される。 2の運上屋はバラサンという岬の袂にあり、この岬は当時厚岸に入港する和船の目印になっていたとのこと。現在は橋を挟んで向こうが新市街。手前が旧市街といった趣。 |
|
|
国泰寺と郷土館の向いにある学校の角に建てられた運上屋跡の石碑。会所となったのは幕府直轄以降。 |
|
|
ノツカマップの風景。岬には熊笹以外何も無い。この湾は岬の途中から見下ろした小さな湾口。海産物の集積所のような小屋が立っている。 岬には小さな灯台がある。”処刑”が行われた場所は不明とのこと。岬の先端へは熊笹を漕いで進んでいくしかない。途中で諦めた。1年に一度イチャルパが行われているそうだ。 ノツカマップでしばし佇む予定だったが、リハーサルが始まるまであと40分ほどしかない。焦って引き返す・・。残念。 |
|
|
現在行くことが可能な日本の最東端。納沙布岬。根室から20Kmほど。ノツカマップからは10Km。海峡を挟んで歯舞の貝殻島へは僅か2km足らず。貝殻島の岩肌や監視小屋がハッキリ見える。風になびく日の丸がここが”国境”であることを(本当は違うが)、感じさせる。
|
第2の舞台、松前に関しては、昔このコーナーで語ったことがありますので参照して下さい。イコトイの絵(松前波響・画)の肖像もあります。ここです。
参考文献
アイヌ人物史(松浦武四郎著、更科源蔵・吉田豊 共訳)
松前波響(財団法人 函館青年会議所)
アイヌの本(別冊宝島EX)
三十七本のイナウ(根室シンポジウム実行委員会編)
新北海道史年表(北海道新聞社編纂)
2003年9月22日「奥尻海峡」
札響に入団して10年。道内くまなく巡ったと思っていましたけど、北桧山の町は始めてでした。北桧山町は北海道南西部渡島半島の付け根に位置する日本海に面した町です。人口は7,000人足らずで、隣接する瀬棚町には奥尻島に向かうフェリーが発着する港があります。その夜は翌日の上磯公演のため函館泊です。瀬棚から江差に抜ける海岸沿いの国道を走るのも始めてでした。
国道から臨むと海を挟んで奥尻の島影が大河の対岸のように横たわります。奥尻がこんなに近い事に驚きつつ、ちょうど島影に陽が沈む刻限に居合わせることができました。
海岸の風景は積丹半島を髣髴とさせ、切り立った断崖と奇岩が多くあります。それらが夕陽に赤く染まっています。日没を見届けるとその刹那に海峡に漁り火がともりました。それはそれは絶景でした。
海と岩以外は戸数数軒にも及ばない集落が点在するのみの海岸沿いの国道を瀬棚から向かうと江差が大都会に見えます。
江差や瀬棚、北桧山など、古くは北前船の寄港地であり、鰊漁でも繁栄を極めた経歴があります。こうした北海道日本海沿岸の街々は今はさびれているものの佇まいは古く、邯鄲の夢といった趣があります。
北海道の地方都市によくあるバラック作りの大型量販店が立ち並ぶ新興国道とは一線を画しています。今度は一眼レフを持ってゆっくり訊ねてみたい場所でした。

2003年8月27日「火星大接近」
6万年振りの火星超大接近に世間は湧いていますね。天体望遠鏡が飛ぶように売れているとか・・。
でもまあ、かつての天文少年に言わせると、世間のパパが張り切って望遠鏡を買って家族に見せても「え?これがそうなの?」と言われるのがオチ。と冷めた目で見てたりします。テレビなんかで世界最大の望遠鏡で撮影した惑星や星雲のド迫力映像を見慣れた目には、家庭向け望遠鏡で覗いた宇宙はあまりにもしょぼいのです。
とは言うものの、一応「見たぞ」という実績を作るために、昨日10年振りに天体望遠鏡を持ち出して火星みました。
高校生の時は天文部というネクラなクラブに所属していました。郵便配達のバイトなどして高橋製作所製、13cm反射望遠鏡(赤道儀つき)というのを買いました。当時の価格で20数万円したのでかなり良いものです。ほったらかしになっているのに昨日はしっかり働いてくれました。
20キロ以上の重量がありますが、高校生の頃はこれをかついて礼文島まで行ったりしました。冬は雪濠を掘って中で何時間も観測したり・・。今じゃ絶対そんな根性ないな・・
久しぶりに望遠鏡に触ったのにレバーの感触は手がしっかり覚えていました。懐かい気持ちに浸れました。それが火星大接近の収穫かな。
2003年8月21日「青春の桜漬け」
今日は軽い話題。
「桜漬け」という漬け物をご存じでしょうか?。よくコンビニの弁当に入っているピンク色の漬け物です。桜色、と言いたいところですが、わたしの好きな桜漬けはまさにピンク色と呼ぶに相応しいおよそ食物の色とはかけ離れた人工的な色彩を放っています。
わたしが初めて「桜漬け」の存在を認識したのは大学の時です。わたしが通っていた大学の食堂の机に、高さ30cm、直径20cmほどのケチャップの空き缶に無造作に詰められ、醤油やソースと並んで置いてありました。要するに『ご自由にお取り下さい』ということです。当時のわたしは、この得体の知れないピンク色の漬け物らしき物体の名称が「桜漬け」というのを知らず「貧乏漬け」と呼んでいました。定食が乗った皿の脇に大量に積み上げ食べていました。
時には100円のライス、30円のみそ汁を買い、無尽蔵に供給されるこの貧乏漬けを添え”貧乏漬け定食”を腹一杯食べたりしました。そうして毎日貧乏漬けのお世話になるうちに、いつかしかわたしはパブロフの犬のようにあのピンク色を見ただけで垂涎する体になってしまったのです。
社会に出てからは、コンビニの弁当や安い定食屋の定食に僅かに添えられるのを見るくらいしか”貧乏漬け”との関りは持てなくなりました。スーパーなどで探しても、それらしい「桜漬け」という名称の商品はあるのですが、買ってきて食べてみるとあの味ではないのです。大根の切り方は厚すぎるし、しその味が濃すぎます。色は上品な桜色。わたしを満足させるには高級すぎるのです。
”貧乏漬け”との再会を果たせぬまま諦めかけていたある日、カレーのルーを買うために友人に教えてもらった業務用食材店に行きました。「もしや!」と思い漬け物コーナーに目を留めると、そう。あったのです。まさにあの”貧乏漬け”です。2kgで470円。有名な漬け物メーカーの「しんしん」が出している「桜漬け」という商品です。2kgの漬け物を個人で消費するのは大変ですが、わたしの青春がぎっしり詰っているのですからその位の重量は当然でしょう。業務用食材店というのが街中で小売り目的に存在しているものなんですね。驚きました。他にも興味深い食材が沢山売ってました。
それからというもの、毎日心ゆくまで「桜漬け」を食べています。買ってきて最初に食べた日は感動して涙が出そうになりました。チープですがさっぱりした塩味でどんな料理にも合う漬け物です。是非お試しください。
 |
 |
|
この状態で売っている。右は30cm定規。 |
タッパーに移し変えているところ。やはり色と量か食物的でない。 |
2003年8月11日「エルムの坂」
札幌市旭ヶ丘というところでわたしは育ちました。20代の約8年間を除き、今日にいたるまでずっとここで生活しています。最近はマンションが雨後の筍のようにドカドカと建設され風景がかなり変わりました。子供のころ遊んだ記憶と共に、この界隈の事はどこに何の草が生えているかまで熟知しています。そういう身にとって街の風景が変わっていくのには寂しさを覚えます。この気持ちはどなたも経験があるかと思います。
今日散歩していると近所にあったエルム山荘という料亭が取り壊されている最中でした。エルム山荘は広大な敷地を持つ超高級料亭です。昔は夜ここの前を通ると黒塗りの運転手付き高級車がズラーっと並んでいるのをよく見ました。いつかはボクもあのエルム山荘で接待されるようになりたいもんだ・・・・、目指せエルム山荘!!と思っていたのに。
周囲は国有林や公園など森に囲まれており、子供の頃この森でよく遊んだのですが、少しでもエルム山荘の敷地に侵入しようものなら、管理人とおぼしきオジサンが物凄い剣幕でやってきて怒られました。後で知った話しですが、エルム山荘は野舞いをするための大きな日本庭園があったそうです。それなら確かに子供の侵入は歓迎されないかもしれません。子供たちからは恐怖の館と恐れられていました。
紫色に塗られた木の壁と特徴のある形の建物の脇に一本の細い坂道があります。近所の住民たちからは”エルムの坂”と呼ばれています。鬱蒼としてなかなか趣のある坂です。

この景色も見納めです。また巨大マンションが起つのかな(鬱)
長引く不況で夜だけだった会席コースにランチも始めたなんていう記事を目にしてたのですが、こんな事なら一回くらい中に入っておけばよかった。後悔してます。
エルム亡き後、次ぎは目指せ”杉の目”!!だな。
【続報】
ただいま入った情報によりますと、エルム山荘は取り壊されているのではなく改装中とのこと。新規オープンは10月頃で”30代から50代の好感度なカップルをターゲットにしたウェディング対応のレストラン&バー”になるそうです・・。失礼したしました(`▽´)
とりあえず巨大マンションにならずに済んでよかったよかった。
2003年8月7日「すっぱいブドウ」
今年は40年振りの冷夏です。数日前の暑い日、オーケストラの練習が夕方からだったのでお昼頃子供を連れて海に行きました。仕事の前に海水浴は気が進みませんが、こうでもしないと今年は海に行かずに終わってしまいそうです。
昔は「大浜」と呼んでいた銭箱の海水浴場もドリームビーチと名前を変えてからは、砂鉄だらけの黒い砂浜、流れ着いたママレモンの容器や半壊したポリバケツ、200円のビールを500円で売る胡散臭い海の家、うっかり裸足で歩くと割れたコーラの空きビンや花火の燃えかすで足の裏を怪我するといった悪のイメージは払拭され、砂は新鮮なものを毎年トラックで運び込み(そうらしい)、砂浜は清掃が行き届きゴミも見当たらず、椅子やテーブルを無料で貸し出す良心的な海の家が軒を連ねるクリーンなスポットに様変わりしました。
今年はさすがに冷夏の影響か、椅子の貸し出しは有料だったので持っていったビニールシートを使いましたが、店の前の砂浜を清掃し客を呼び込む努力を怠らない海の家に敬意を払って、ビールと焼きそばとホットドックを買いました。食べ物はちゃんとわたしのスペースまで運んで来てくれます。これこそ企業努力ですね。
海で食べる物といえばやはり焼きそばです。申し訳程度の肉とキャベツの芯が若干入っただけのソース味の濃い焼きそば。海で食べるのはこれじゃなくちゃいけません。もしフカヒレ入り四川省風高級アンかけ焼きそばが出てきたら食べる気がしません。昔は焼きとうもろこしもよく見かけましたが最近はあまり見ませんね。そういえばジンギスカンも最近あまり見なくなりました。海でジンギスカンの臭いを嗅ぐと無性に食べたくなります。あの”なまら濃いタレ”の味も海に合います。
子連れで海に行って気が付いた事が一つ。その日は11時位に着いて2時前位まで海にいたのですが、私たちが着いた午前中には浜は家族連れで賑わっていました。若者は全然いません。平日だし、世の若者たちはきっと今ごろ額に汗して働いているに違いない・・・。と思ったのですが、食事が終わり1時位になると家族連れは潮が引くように浜からいなくなり、代わりにカップルや若者グループがワラワラと押し寄せて来ました。さっきまで子供と砂で堤防など作って遊んでいたわたしは完璧に大衆にとけ込んでいたのですが、マイスペースに戻ってみると周囲はカップルたちに席捲されています。そう、わたしが堤防作りに熱中している間に浜の様子はすっかり変わっていたのです。
下のグラフをご覧ください。これはわたしの主観だけを元に作成したドリームビーチの人口推移の分布図です。X軸(横軸)の数字は時間。Y軸(縦軸)は人数。赤い線は家族連れ、緑は若者、青い線はビーチ全体の人口を現しています。
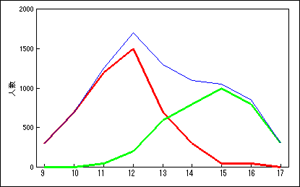
グラフが示すように、浜の人口分布の中心は午後1時頃を境にして家族連れから若者に移ります。家族連れは午前中から来て浜でお弁当を食べたら帰るのです。若者たちは早起きして海に来るなんていう行動パターンはとりませんね。確かに・・。
堤防作りから戻ったわたしは周囲を取り囲むビキニギャルたちをチラチラと横目で盗み見ながら、グリム童話の「狐とブドウ」の話しを思い出しました。狐がたわわになるブドウの実を取ろうとするのですが、どうしても手が届きません。狐はやがて「ふん、どうせあのブドウは酸っぱいに決まってる」と思い込むことにして取るのを諦めます。いわゆる”すっぱいブドウの理論”ですね。
「子連れのお父さんは周囲を取り囲むビキニギャルに声をかけたくても到底できるわけがありません。そこでお父さんは思います。ふん、どうせ頭悪くて気が強くてわがままなんだろ!」
10数年前にその当時の彼女と海に行った時は、このお父さんの気持ちは分からなかったな〜。俺も大人になったもんだ。

2003年8月1日「夏の夢」
漠然と多い、少ないと感じているものを敢えて数字で表して喜ぶ。わたしには昔からそういう癖というか楽しみがあります。
いつも組んでいる弦楽カルテットの練習中、休み時間にヴァイオリンのM原T彦さんが缶コーヒーを飲みます。彼は缶コーヒーが大好きでいつも飲んでいるという話題になりました。健康に悪いから飲み過ぎに注意した方がいいよ。普通はここで話しが終わるところですが、それではおもしろくありません。250mlの缶コーヒーに含まれる砂糖は角砂糖6個分と聞いた事があるので、それで計算して1年間に摂取する砂糖などの量を本人に教えてあげましょう。彼は1日に平均3本の缶コーヒーを飲むそうです。ということは、1年間に2190個の角砂糖を食べることになります。コーヒーの料は278リットル、敢えてガロンに訳すと、278を3.8で割って72ガロンのブラックコーヒーを飲む事になります。一度に2190個の角砂糖をむさぼり食いながら72ガロンのコーヒーを飲み干す姿を想像すると笑えますね。
札響の楽員ではないのですが、東京で活躍している親しいヴァイオリニストのKさんが組んでいる四重奏団には、チェロにとても理屈っぽい人がいて困るそうです。1回の演奏会のために要する練習回数は優に20回を越え、練習一回にかかる時間は5〜6時間というほどの密度の濃いことを10年以上やりつづけています。「こんなに練習必要なんだろうか?」、「チェロの人の話しが長がくてさ〜、それで時間使っちゃうんだよ」などと電話の向こうから聞えるKさんの愚痴をフンフン・・と聞き流しながらわたしは電卓片手に計算を始めずにはいられません。彼らは1年に4回のそうした自主演奏会を開きますから、カルテットを組んでから今までの総練習時間は4,800時間。仮に飲まず食わず寝ずで練習し続けても200日間。そのうちチェロの人が話していたであろう時間は、Kさんの報告から推測するに延べ800時間。あり得ない事ですが面白いので連続させてみると、チェロ氏は飲まず食わず寝ずで1ヶ月以上チェロも弾かず話し続け、Kさんは同じく飲まず食わず寝ずで1ヶ月以上ヴァイオリン片手にふてくされていた事になりその姿を想像すると笑えます。
ヘビースモーカーが今まで吸ってきた煙草を繋げた場合の総延長や、トイレの個室占有時間が長い人が一生の間にトイレで過ごす時間など、計算するとおもしろい事はまだまだあります。
さて、今日(8月1日)はサマージャンボ宝くじの発売最終日でしたね。(これを読んで「あ、買いわすれた!!」と思ったあなた。お気の毒さまでした(`▽´) )。宝くじこそ計算せずにいられないものの権化ですね。宝くじ1等の当選本数はご存じのとおり1000万組に1本ですから当選確立は1/10,000,000。これだとあまりにも当る気がしないので2等まで入れる事にしましょう。2等は1000万組に5本ですので、1等の1本と足して1000万組に6本の当たり、・・っていうことは、6/10,000,000で約分すると、ん〜割り切れない。まあここは自分に厳しく分母を切り上げてっていうことで、1/1,700,000の確立で当るってことにして、わたしの場合、いつもバラ10枚、連番10枚の計20枚買うので、確立は、1/85,000。
かなりいいところまで来ましたね(どこがだ!)。と一人ボケツッコミをやってしまいたくなる程の確立の悪さにしばし唖然。6000円出費して20枚の宝くじを買い、1000万組に計6本含まれる1等と2等の賞金の平均は、(一等(2億)×1+二等(1億)×5)÷6=約1億2千万円。それでこれをわたしの当選確立で割ると、約1400円。
ふーむ。なるほど。わたしは1400円まで期待していいわけだ。1400円の当選を期待するのはわたしの当然の権利なわけだ。今日は家族3人で近所のスーパーへの買い物ついでに宝くじを買いましたが、帰りの車では当然、「3億円当ったったら何買う?」という超小市民的な話題で盛り上がるわけです。大きな夢を語ると外れる気がしたので、わざと小さな夢を・・。わたしはさっきスーパーで買うか迷った980円の使い捨て腕時計。妻はカラスに突つかれて破れた自転車のサドル。これも980円。3才の娘はセーラームーンの”ガチャポン”2回で200円。いやまてよ、これでは1,400円をはるかにオーバーしているな。3人で計2160円。こんなささやかな望みを抱く権利もないということか・・。そうか。よーし分かった。そっちがその気ならな、こっちはな・・・・・・・・・・・・
2003年7月29日「謎の現象」
昔から疑問に思っている事があります。それは「なぜ本屋に行くとウン○をしたくなるか?」ということです。ウン○というのはいわゆる一つのもしくは複数の”大きい方”のことです。
はじめてこの不可思議な生理現象に気が付いたのは、今を遡る事二十数年前の小学校高学年くらいの頃です。本屋に行って一人で読みたい本を探すのってこの頃からじゃないですか。近所のスーパーの本売り場に行っても、街の大きな本屋に行っても、本を選び初めて数分後に必ずもよおします。やがてよく行く本屋のトイレは常連になり、お気に入りの個室の壁の落書きまで覚えてしまうほどになりました。高校生くらいになり知恵が付いてくると、インクと紙からくるあの本屋独特の臭いとこの生理現象の因果関係を疑い始め、それは半ば確信に近いものになっていました。
東京で大学時代、フリー奏者時代を送っていた頃はよくCD屋に行きました。実はCD屋でもこの摩訶不思議な生理現象が起こる事に気が付いたのです。ここで”本屋のインクと紙の臭い説”は崩れ去った訳です。この頃よく行っていた秋葉原の石丸電気レコード館は、東京でも一番品揃えがいい部類のCD屋で、おまけに沿線沿いに住んでたのでよく行きました。しかし!。ここの店、売場面積の割にトイレの数が異常に少ない。本屋やCD屋に行ったらまずトイレのありかを確認してから選びにかかるのですが、ここはたしか5階建の建物のそれぞれのフロアに男用、女用といった具合にトイレが配置されていて、要するに隔階にしかトイレがないのです。しかも男用には個室が一つしかありません。
そもそも男トイレは個室が少なくて2つあれば多い方ですね。3つだとかなりゴージャスです。それに何故か男は一旦個室に入るとなかなか出てきません。個室占有時間がとても長いのです。このわたしの不可思議な現象はもよおし方がとても激しくて、さっきまで全く便意など感じていなかったのに突然怒濤のように押し寄せてきます。便意を感じてトイレに行き、一つしかない個室が塞がっていた場合は、まさに七転八倒、地獄の悶絶責め状態で、漫画でよくあるお尻をおさえながらトイレを捜し回る姿をリアルで演じなければならない状態に陥ることは必至です。
その姿を演じるのはさすがにかなわないし、想像するのもおぞましい万が一の事態に備えて、個室数の少ないこういう店舗の場合は事前に予備のトイレも確認しておきます。この東京のCD屋の場合はたしか3階位に隣の家電館への渡り通路があって、家電館には各階に個室が2つあるトイレがありました。当時はCD屋や本屋に寄る時は仕事帰りか学校帰りで常にチェロケースを担いで行動していたので、大きなチェロケースと共にトイレの個室に入っていたので、通常より狭い個室の場合は苦労しました。家電館の個室はかなり狭かったです。
あの小学生の頃から20数年。今でもこの謎の生理現象は続いています。何故そうなるのかという謎も解けていません。そしてこの現象は、はたしてわたしだけのものなのか、それとも多くの人と共有できる悩みなのか。それも是非知りたい所です。本屋とCD屋ではまずトイレの場所を確認するというのは私の中では既に無意識の行動になっています。どなたかこの生理現象を説明できる方がいたら教えてください。そして悩みを共有できる方がもしいるなら、是非語り合いましょう。
2003年7月27日「危険な季節」
夏ですね。夏といえば街はミニスカの女性で溢れます。街中で車を運転していると歩道を歩いているミニスカ女性が目に飛び込んできます。思わず視線が釘付けになりますね。これはボクだけではないと思います。全ての男性に言える事ですね。まず見るのは当然脚になるわけですが、ボクの場合脚全体をパッと見た後、視線は太ももへ移り太ももからお尻周辺を凝視してしまいます。ボクの場合と言いましたが、これもほとんどの男性に当てはまるでしょう。
太ももからお尻周辺をひとしりき凝視した後は腰から上をすーっとなぞり顔を見ますね。これも多くの男性が辿る道筋だと思います。そう。ミニスカ女性への視線は必ず下から上です。これは普遍的な法則と言ってもいいです。女性が後ろ姿だった場合、特に後ろ姿が綺麗だった場合はどうしても顔を見たくなります。顔を見なければ完結した気がしませんよね。自分の車がその女性を追い越すと視線はバックミラーへ移りますね。これに関しても論を待たず全ての男性がそうだと思います。電柱などが邪魔で見れない事もよくあるのですが、そういう時は信号待ちでその女性が車に追いつくのをじーーっとバックミラーを見ながら待ちます。信号が青になってしまい、女性の顔を確認できないまま車を発信させるときの何とも中途半端な気持ちは男だったら誰でも経験がありますね。
そう。これで明らかな様に街を歩くミニスカ女性は車を運転する男性の視線をかなりの時間に渡って釘付けにしてしまうのです。ミニスカ女性が前から歩いてきた場合、脚全体から太ももを凝視、顔を確認までの所要時間は約3〜4秒と考えられます。4秒とした場合、これは時速40kmで走向する自動車が44メートル進む時間に相当します。女性が後ろ向きだった場合状態はさらには悪化し、脚全体から太ももを凝視、バックミラーに視線を移し顔確認までの所用時間は上手くいった時でも10秒は必要です。これは時速40Kmで走向する自動車が実に111メートルもの距離を進む時間に相当してしまうのです。
危険を察知してから車が停止するまでのいわゆる停止距離は、乾いたアスファルト路面でも時速40kmで走向時、約20mが必要です。ミニスカ確認中に危険があった場合、ドライバーは危険を認識する事もなく大きな事故を引き起こしてしまう可能性がありますが、ミニスカ確認終了直後に危険を察知した場合でも、車が停止するまでにはミニスカ確認に要した時間中に車が走向した距離に、自動車本来の停止距離が加わる事を忘れてはいけません。雨の日の濡れたアスファルト路面や砂利道ではこの距離はさらに伸びます。
こうしたデーターをふまえ、男性ドライバーは夏の運転には充分注意しましょう。
2003年7月24日「トーク付きコンサート」
今日はいつもゲストで呼んでもらってるFMアップル出演のあと、地下街コンサートでカルテットの本番だった。そのラジオのお蔭もあり最近は「荒木は話しが上手い」という事になってきて、トーク付き室内楽コンサートでのお話しはだいたいいつも担当している。ポピュラーな曲を演奏する割りとくだけた感じの室内楽やソロコンサートでは「トークもお願いします」と依頼される事が圧倒的に多いのだ。仲間うちでは多少インチキ臭いという評価も無きにしもあらずだが、人前で話すのはもともと嫌いじゃないし、とにかくやり続けているうちにある程度は上達してくるものだ。
コンサートでトークを続けているうちにネタも増えてくるし、お客の反応を見ながら話しのディテールを変えたりしてけっこう楽しい。『蝶ネクタイを忘れて靴下を首に巻いてステージに出た』なんていうオーケストラの失敗談とか、楽器紹介なんかもお客の笑いを取りながら出来るようになった。
ただ、よく思うのが、楽器を弾く時に使う脳と話す時に使う脳は違うのではないかという事。トーク付きコンサートを上手くこなすのは、ただ話すだけ、ただ弾くだけというとは全く違う技術を要求される。コンサートでトークをやりはじめの頃はこの勘所というか一種のコツが飲み込めなくて随分苦労した。その頃はコンサートで話すのには慣れていないとはいえ、「俺ってこんなに話し下手だっけ??」と思うくらい上手くいかない事も度々だった。
そこで”使う脳が違う”という話しになってくる。ちなみにこの話しに関しては脳について本を読んだとか、そういう学術的な根拠は全くありません。あくまで私の想像です。どういう事かというと、例えば楽器を演奏している最中に「次のトークは何話そうか」と考えちゃうともうダメ。音楽的な脳が休止状態に入る感じがして弾いていても音楽に集中できない事はおろか、ボケ〜〜っと霞がかかったように楽譜が読めなくなってくる。テンポも取れない、音程も取れない、ケアレスミスをする、という最悪の状態に陥ったりする。一方で演奏に集中しすぎてお話しの脳が完全に休んじゃうと、演奏が終わって次のトークの時にすぐ滑らかに話すのはとても無理でシドロモドロになってしまう。お話しが終わってから演奏に突入するときも最初の1ページ位はやはり音楽脳にはボケ〜と霞がかかっている。札響の名曲コンサートなんかで指揮者がお話し付きでコンサートを進める事がよくあるが、大変だろうな、といつも思いながら見ている。実はかなりの負担を強いていはずなのだ。
近ごろは考えなくても話せるいわゆる”持ちネタ”を増やす事こそがトーク付きコンサートで恥をかかない唯一の方法という事が分かってきた。演奏している時は「次ぎはあのネタでいこう」とさえ思っておけば弾きながら話しを組み立てる必要も無い。また、話している時間もマシーンの様にネタを披露さえしていれば”お話し脳”をフル回転させる必要もなく、次に演奏に入った時にスムーズに”音楽脳”か起動してくれる。この脳のスイッチの切り替えこそが秘けつらしい。
切り替えが割りと上手くいくようになってからは、お客さんからお話しが上手とお褒めの言葉に預かれるようになってきた。ただし悩みというか新たに分かった事がひとつある。トークが褒められれば演奏までは褒めてもらえない、ということだ。これは”演奏者”としてはかなり深刻である。「あなたは道を誤った」とまで言われる始末。かと言ってヘロヘロになりながら下手な話しをすると「トークがいまいちだったね」と言われるし・・。一体俺はどうすればいいんだ!!。(゚ロ゚;グハッ
2003年7月21日「カラオケ」
今日から”札響ポップス”の練習が始まりました。クラシックの演奏家って意外と歌謡曲に疎い人が多くてカラオケ行ったことないっていう人も珍しくありません。そうじゃない人も沢山いるけど・・。ボクはカラオケ大好きで、行ったら最後喉が枯れるまで歌い倒します。バブルの頃は年齢的にも20代で遊びたい盛りだったので(今でもそうですが)、本当にカラオケよく行きました。最近はめっきりカラオケ行く機会が減ったので、今だにレパートリーはバブル当時の遺産に頼っている状態です。
よく歌うのは、「ハナ肇&クレージーキャッツ」関連(これって植木等で検索すると出てこないんだよね〜)、とか、永井濠系のアニソンで”マジンガーZ(日本語&韓国語)”、”デビルマンの歌”を熱唱。田原俊彦系。ラッツ&スター系。デュエット曲は”マイクハナサンズ”系のメドレーを始めとして、「もしかしてpart2」、「別れても好きな人」クラスの懐デュエが多いです。演歌では「中の島ブルース」などのクールファイブ系。裕次郎もけっこう歌うかな。
やっぱりカラオケ行くのはなんといっても同世代が盛り上がりますね。同じレパートリー共有してるからね。ライバル意識も芽生えるし。カラオケ置いてるスナックで知らない客と張り合うのもいいけど、やはりプラスマイナス10才位の同世代でカラオケボックスで小技効かせながら歌いまくるのが楽しいですね。
最近はカラオケ行く機会も減って欲求不満たまってます。札響ポップスで歌謡曲が出てくると「そ〜〜じゃないんだよ!!」と自分流の解釈で歌いたくなります(笑)
さ!誰かボクと勝負しないかい!?
2003年6月20日「ジェンダー」
最近新聞でよく目にする用語に「ジェンダー(性差別文化)」っていうのがありますね。差別っていう言葉には当然ながらマイナスのイメージがあるし、それどころか人種差別はじめ、とんでもなく非人道的で絶対にしちゃいけない事という風に認識してますが、試しに広辞苑なんぞを引いてみると『差をつけてとりあつかうこと。わけへだて』と、意外とソフトな表現だったりもします。
わたしには3才の娘がいるのですが、娘が寝る時などに物語をせがまれる事があります。スタンダードな昔話をアレンジして話してやるのですが、最近話したのにこんなのがあります。
むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがいました。
おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯にいきました。
おばあさんが川で洗濯をしていると、上から大きなイチゴがドンブラコッコドンブラコと流れて来ました。
おばあさんは「あれまあ、なんて大きなイチゴなんでしょ。持って帰っておじいさんと食べましょう」と言って、イチゴをゴロゴロと転がして帰りました。
家に帰っておじいさんと一緒にイチゴを切ると、中から男の子が出てきました。
イチゴから生れたのでその子を”もも太郎”と名づけました。
(ここで娘から「イチゴ太郎でしょ!」とツッコミが入る)
あ、そっか・・。イチゴ太郎はやがて大きくなって、おじいさんの芝刈りを手伝えるまでになりました。
そして、おじいさんとイチゴ太郎は山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に行きました。
おばあさんが川で洗濯をしていると、上からおおきなバナナが流れてきました。
おばあさんは、バナナをずりずり引きづって持ち帰りました。
おじいさんとおばあさんとイチゴ太郎は、大きなバナナの皮をむくと中から可愛い女の子が出てきました。
バナナから生れたのでその女の子をバナナ姫と名づけました。
バナナ姫はやがて大きくなって美しい娘に成長し、おばあさんの洗濯を手伝えるようになりました。
(そこで、近くで聞いていた妻から「それってジェンダーじゃない?」とツッコミが入ります。)
ボク 『え?なんでジェンダーなの?』
妻 『だって女は洗濯、男は芝刈りって決めてかかってるじゃない。新聞にそんなような事 書いてあったよ』
ボク『そっか〜、これもジェンダーか・・』
(そこで話しの方向性を少し変えることにしました)
イチゴ太郎とバナナ姫は村の生活が退屈になり都会にでることにしました。
イチゴ太郎は助産士になりました。苦労して産院を開きましたが男性助産士と聞いてなかなか妊婦さんがきてくれません。やがて産院は潰れてしまいました。
バナナ姫は日本初の女性運転士になりました。美しいバナナ姫はマスコミなどに大々的に取り上げられましたが、日々の取材やストーカーまがいのファンができたり、匿名掲示板などの心ない書き込みですっかり神経をやられてJPを辞めてしまいました。
そうしてイチゴ太郎とバナナ姫は村に帰り、おじいさんとおばあさんと一緒にいつまでも幸せにくらしましたとさ・・。
めでたしめでたし。
”男らしさ”、”女らしさ”っていうのを美徳と思っている者としては、今問題になっているジェンダーにははっきり言って違和感を感じます。男らしさや女らしさをあえて差別のカテゴリーに入れて男女を画一化してしまう事にそろそろ歯止めをかけませんか?と思います。男性助産士や女性運転士がいけないって言ってるんじゃありませんよ。でも例えば”保母”がダメで”保育士”って言ってみたり、”看護婦”がダメで”看護士”って言ってみたりするのには文化的な視点でも反対だし、敢えて名称まで変えて画一化を推進する必要はないだろ、と思います。
ジェンダー系の記事を目にすると「萎えるな〜」と思います。女性は出産で仕事を中断しないといけないわけだし、これってあたりまえですよね。そのあたりまえが崩れると誰が子供産むんでしょ・・。女は男より弱いから男は頑張れるわけですよ。少子化に歯止めって言っても産休制度だけ整えても全然だめ。女が働き続けるためには乳児保育、幼児保育、学童保育、ってまだまだ完璧に整備しないといけない事山積みじゃないですか。完璧にできますか?。できないでしょ。男女画一化だけ先に進めたら日本は滅びます。
”男らしさ”や”女らしさ”を美徳と捉えることは先人からの知恵だと思います。男を萎えさせて専業主婦が損した気持ちになる現代の”男女画一参画プロパガンダ”には大反対!。
おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に行くんだよ!!。文句あるかっ!
2003年1月29日 「チェロアン」
今日はFMアップルの出演日でした。長らく頓挫していたHPのこのコーナーもやっと復活しようっていう気分になりました。なにしろ昨年末からの「札響破綻・解散も!」騒動の渦中にいたので憔悴しきって人格が変わるほど大変でした。新聞などで「労組が人件費削減を受け入れ破綻回避」といった具合に報道されていましたが、まだまだ予断は許さないものの一息つける状態になりました。といっても本当に大変なのはこれからなんですけどね。ご心配や応援本当にありがとうございました。札響BBSでの沢山の書き込みは見ている人も多いですし、多くの良い意味で影響があったと思います。詳しいことなどまだご報告できませんが、札響の変化をお楽しみ。
で、FMアップルの出演記録は別コーナーを設けていたのですが、更新や送信が煩わしくなり停滞する元なのでこのコーナーに移してしまいました。更新が滞っている間は放送の方は札響の話題が中心になっていたのですが、今日はチェロアンサンブルについて話しました。クレンゲルという作曲家をご存じでしょうか?。DJの岡部さんがご存じなかったのが意外というか、それほどマイナーな作曲家なんだな、と再認識しましたが、チェリストの間ではとっても有名な人です。
チェロアンサンブルの名曲も多数ありますし、チェロコンチェルトも何曲も作曲しています。またチェロの教則本でも有名です。中でも12人のチェロのための「讃歌」はチェロアンサンブル曲の名曲中の名曲です。チェロコンチェルトは作曲当時は本人が弾くために作曲されたんでしょうけど、今はもっぱらチェロ学習者のための勉強用コンチェルトとして親しまれています。19世紀にゲバントハウス管弦楽団の首席チェロ奏者として活躍した人です。
こうしたチェロ界の中だけで有名な人は、例えばチャイコフスキーの「ロココ風主題による変奏曲」を献呈されたフィッツェンハーゲンとか、ボッケリーニのチェロ協奏曲を改編して改編版の方が現在演奏されているんですがグリュッツマッハーという人とか、もう少し有名どころでは「妖精の踊り」という小品が有名なポッパーという人とか、オペレッタ「天国と地獄」で有名なオッフェンバッハも歌劇場付きオーケストラのチェリストで、こうした人たちは皆、チェロアンサンブルの名曲を残しています。
中にはサロンで弾くために作曲されたような退屈な曲もあるんですが、先述のクレンゲルのような名曲もあります。そもそもチェロアンサンブルは2本で弾くためのものから12本で弾くためのものまでオリジナル曲が多数存在するディープな世界なのですが、チェロという楽器の音域が「低い」と感じる音から「高い」と感じる音まで出せることと音域の広さから、同種楽器のアンサンブルとしてはとても有利な立場にあるので、これほど多くの曲が作曲されて楽譜も出版されたんだと思います。
今日のようにCDが沢山出るようになったのはなんといっても「ベルリン・フィルの12人のチェリストたち」の存在が大きいと思います。たしか1980年くらいだったと思いますが、彼らがヴィラロボスのブラジル風バッハを録音したレコードを出して一世を風靡した事が今日のチェロアンサンブル隆盛の礎を築いたと思います。カメラメーカーのキャノンのCMで真っ白い部屋でベルリン・フィルのチェロのおじさんたちが12人で弾く中、「フォーカスが早いんですよ!」というセリフとともに誰かにピントが合うCMだったように記憶してます。
チェロアンサンブルご存じない方は是非お聴きあれ!。私のお薦め曲を列挙しておきますのでご参考に。
ヴィラ=ローボス ブラジル風バッハ第1番(チェロ8本or12本)
ヴィラ=ローボス ブラジル風バッハ第5番(チェロ8本andソプラノ)
クレンゲル 四つの小品(チェロ4本)
クレンゲル 讃歌(チェロ12本)
ポッパー レクイエム(チェロ3本andピアノ)
フンク 組曲 ニ長調(チェロ4本)
フィッツェンハーゲン アヴェ・マリア(チェロ4本)
フランセ オーバード
上の曲を全部「あ、あれね・・」と言って鼻歌で歌えたらアナタはコアなチェロアンヲタクです(笑)。他にも良い曲たくさんありますし、編曲モノはもう沢山CDで出てます。
それから、オーケストラの曲の中にもちょっとしたチェロアンサンブルありますよね。例えばウィリアム・テル序曲の冒頭の日の出のチェロ5重奏とか、チャイコの序曲「1812」の合唱が入らないバージョンの冒頭のチェロ4重奏とか、プロコフィエフの交響曲第5番の4楽章の最初のところとか、オペラでは「オテロ」に有名なチェロ4重奏があります。他の楽器ではちょっとないですよね(自慢げ)。